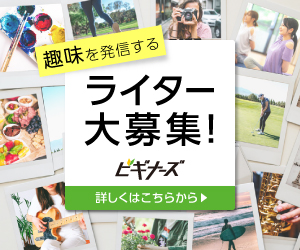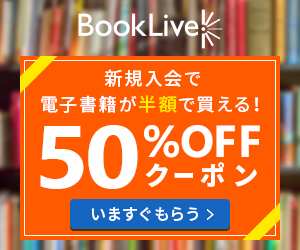更新
[保存版]フルート初心者必見!基礎知識を身につけて趣味にしよう
![[保存版]フルート初心者必見!基礎知識を身につけて趣味にしよう](https://www.rere.jp/beginners/uploads/2017/09/c7d0b216253729f0dad7ca403c6ab494_m.jpg)
※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
優雅で軽やかな音を奏でるフルートは、吹奏楽やオーケストラには欠かせない楽器です。また、クラシックの他にジャズやポップスなど、さまざまな曲が演奏できるため、楽器初心者の方にもフルートは長年人気の楽器です。
目次
フルートは初心者でも演奏しやすい楽器

フルートは、管楽器の中でも購入しやすい価格帯の機種が多いことから、初心者でも手軽に始められる楽器です。横に構える独特のスタイルに、長年憧れている方も多いことでしょう。
フルートは一般的なコンサートフルートの他に、アルトフルート・バスフルートなど中低音を出せるものがあります。また、甲高い澄んだ音色のピッコロもフルートの仲間です。吹奏楽やオーケストラでは、フルート奏者がピッコロを兼任することがあります。
フルートは最初の一音を出すのが重要ポイント。コツとしては、口を横一文字にし、ストローほどの幅で斜め下方向に息を吹き出します。ペットボトルの空き瓶の口を「ポーッ」と鳴らしてみたことはありませんか?あの感覚で、最初の一音が安定して出せるようになったら、次に指使いの練習をしましょう。
初心者なら聴いておきたいフルート名曲3選

実際にフルートの音色を聴いてみましょう。
透明感のある上品な音色が美しいですよね。他にもフルートの音色が綺麗な楽曲はたくさんあります。フルートは吹奏楽やオーケストラなどでクラシックを演奏するのはもちろん、ジャズやアニソン、ポップスなど様々なジャンルの音楽で欠かせない存在です。
フルートの魅力を存分に堪能していただくためにおすすめの曲をご紹介しています。どのようなジャンルを演奏することができるのか知ると、フルートにますます挑戦したくなると思います。
フルートは金属製だけど木管楽器

銀色に輝くフルートは木管楽器に分類されます。初心者であれば「金属製なのに木管楽器?」と考えるのも無理はありません。ここでは、フルートが木管楽器である理由を解説します。
フルートが木管楽器である理由
フルートは金属製なのに木管楽器なの?と疑問に思われる方も多いでしょう。そもそも木管楽器は、リードを使い演奏者の唇を使って音を出す楽器のことを指します。フルートは木管楽器の中でもノンリードとも呼ばれています。フルートの場合、管のエッジに当たった空気の渦を利用し音を出す仕組みで、別名「エアリード」とも言われます。木管楽器は材質を意味するのではなく、あくまでも奏法によって分類されているというわけです。
フルートの歴史
バロック時代までは縦型の笛をフルートと呼んでいましたが、18世紀半ば以降、現在のような横向き(フラウト・トラベルソ=横向きのフルート)が主流になります。1847年のパリ万博でドイツ人の楽器製作者テオバルト・ベームが現在のような金属製のフルートを発表。以降「ベーム式」と呼ばれるこの大改良によって、フルートは安定した大きな音が出せるようになりました。
フルートの種類
フルートには同属楽器と呼ばれる仲間の楽器があります。オーケストラや吹奏楽を経験したことがある方はピッコロなら見たことがあるかもしれません。
比較的高音の音域を鳴らす楽器というイメージがあるフルートですが、実は同属楽器のコントラバス・フルートはチェロやトロンボーンの音域に近い低音を鳴らします。音域は通常のフルートの2オクターブ低い音まで出すことができます。
フルートとは思えない渋くてカッコイイ音を鳴らし、なんと数字の『4』のようなカタチをしています。全長180cmもあり、重さが約4kgもある大型楽器です。
この他にも知るとおもしろいフルートの同属楽器はまだまだあります。フルートは同属楽器だけで演奏をするアンサンブルもできるので、種類を知っておくとさらに楽しさが増しますよ。
知っておきたいフルートの各部名称

どんな楽器でもそうですが、楽器の各部にはそれぞれ名称と役割があります。もちろんフルートも例外ではなく、大きく分けて3つの部管があります。1つずつの名称と役割を覚えれば必ず上達のスピードが向上するので、ぜひ初心者のうちに覚えてしまいましょう。
フルートで最も大事な「頭部管」
息を吹き込む部分の頭部管は、フルートの命とも言えます。歌口にはリッププレートが乗っており、ここから息を吹き込みます。ヘッド部分の内側には「反射板」があり、歌口の中心から反射板までは17mmが適切とされており、少しでもずれるとピッチ(音階)に大きく影響します。吹く前にまめなチェックが必要です。
たくさんのキーが連なる「胴部管」
胴部管にあるフルートのキーは、とても繊細な構造になっています。各キーを繋ぐ連結部分には力を加えないよう気をつけましょう。胴部管のキーにはリング状になっている「オープンキー」と、全て塞がっているタイプの「カバードキー」があります。フルート初心者の方には、しっかり抑えられるカバードキーがおすすめです。
安定した音をコントロールする「足部管」
一番短いパーツながら、フルートにとって大切なキーが含まれるのが「足部管」です。フルートの足部管は通常3キーの「C足部管」ですが、より低い音が出せる「H足部管」もあり、こちらはキーが4つです。H足部管を必要とする曲は稀なので、初心者は通常のC足部管だけで十分演奏ができます。
フルート初心者におすすめの補助機能&練習場所

始めたばかりの頃はどんなフルートを使えばいいのかや、どこで練習すればいいのかと何をするにしても悩んでしまいます。そこで、簡単ではありますが初心者におすすめの補助機能と練習場所についておすすめさせていただきます。
フルートの音階について
フルートは3オクターブの音が出せます。初心者はハ長調(普通のドレミファ)から運指を練習するのですが、その時に避けて通れない音「高音域のミ」があります。フルートの構造上、経験者でも綺麗に出すことが難しい音ですが、補助機能のあるフルートであれば初心者も綺麗なミが出せるようになります。
高音のミを出すための「Eメカニズム」とは?
第3オクターブのミ(高音域のE)が出しにくいフルートですが、これを補うのがEメカニズム(以下Eメカ)と言われる補助機能です。YAMAHA-FL311は初心者用フルートでEメカが付属している機種です。出しにくい音が一つでもあると、練習が続かなくなりがちです。また、Eメカは後から付けたり外したりが出来ませんので、初心者であればEメカ付きのフルートを選んだ方が無難でしょう。(YAMAHA FL-211はEメカが付いていません)
フルートは音が大きい?初心者向けの練習場所
優しげな印象のあるフルートですが、意外に音が大きいのが特徴です。初心者のうちは特に高音部が安定せず、いわゆる「ピーヒャラ音」が耳につきやすくなります。金属ですので水辺のある公園などは避け、楽器練習OKのカラオケルームや、楽器店の練習ブースを借りるのが無難でしょう。
練習場所についてはこちらでも詳しくご紹介をしています。実は身近な場所でも練習ができるので、自主練習にも困りませんね。
フルートクリーニング用品おすすめ3つ

クリーニングロッドとスワブ
フルートにはたいてい、クリーニングロッドが付属しています。長い棒の先に穴があり、そこに大判のガーゼをはさんで、ロッドに巻きつけて管の水分を拭き取ります。写真のように筒状に縫われたクリーニングスワブとロッドであれば、手軽に掃除ができて便利です。
クリーニングペーパー
フルートのキーの裏にある「たんぽ」は呼気による大量の水分を含んでいます。放っておくと タンポの劣化やカビの原因にもなります。クリーニングペーパーをキーと本体の間にはさみ、しっかりと水分を取り除きましょう。
シルバークロス
フルートは銀もしくは銀メッキ製です。皮脂が付いたままですと錆の原因にもなりますので、専用のクロスで磨いてからケースに入れるようにしましょう。
フルートの楽譜の読み方と継続できるおすすめ独学方法

フルートが初めての楽器という音楽初心者の方は、『楽譜が読めない』『続けられるかわからない』と不安に感じることがあると思います。これにはフルートを実際に経験してみるということが一番の解決策だと思います。
実際にフルートをお手頃な料金でお試しをする方法や楽譜の読み方、独学方法について解説します。
フルートはもともと大人でも始めることができる人気の趣味の1つなので、心配しすぎず、楽しみながら練習してみてくださいね。
フルートの楽譜はピアノと同じでシンプル
管楽器の場合、B♭調やE調というように出すことができる音域が変わります。音域が違うと楽譜も異なります。例えばサックスはB♭調でピアノはC調です。サックスで『ド』を出すとピアノで同じ音は『レ』になります。
少しややこしいですが、フルートの場合は皆さんにも馴染みが少しはあるピアノやリコーダーのC調と同じです。楽譜は音符の位置とフルートの運指を覚えることができたら少しずつ読み進めることができます。
自分のペースで練習してみましょう。
購入前にフルートをレンタルしてお試し期間を設けよう
フルートは管楽器の中では比較的お手頃な楽器ではありますが、それでも新品を購入する場合相場は数万円かかります。
これまで様々な趣味や習い事を始めて、挫折してしまったという方には少しハードルが高いと思います。
「続けられるか心配」「でも挑戦してみたい」「演奏してから決めたい」という方におすすめなのがレンタルサービスの利用です。
レンタルをすると指定した期間だけ料金を払えばよいので、費用がかかる趣味も気軽に始めることができます。
サービスによって条件が異なりますが、全国に対応しているサービスもあるので、1度は使ってみることをおすすめします。
続けられるか心配…独学でフルートを上達するコツ
楽器の上達には個人差がありますが、基本的に地道な努力が必要です。ただ、お気に入りの曲を演奏したり、大きなステージに立つことに憧れたりすることでどんどんフルートの魅力にハマっていきます。
独学でもフルートを継続するには3つのポイントがあります。どれも簡単で基本的なことなので、みなさんも実践ができると思います。
またフルートはコンパクトなので持ち運びやすく、練習しやすい楽器です。フルートの特徴を知ることで、独学でも続けられる自信をつけましょう。
フルート基礎練習に便利な初心者向けテキスト

独学で早速学びたいと考えている方向けに目的に合わせたテキストを紹介させていただきます。まずは自宅で試してみたい方へおすすめです。
基礎をしっかり練習
初心者向けフルート教室に通いたいけど時間がない…そんな時はDVD付属の練習テキストがおすすめです。本書は、唇の動き(アンブシュア)の動画も含め、丁寧に解説されています。練習曲の楽譜もありますので、継続して練習しやすいテキストです。
CD付きの楽譜で本格練習
フルート初心者でもある程度運指を覚えたら、定番ポップスに挑戦してみませんか?『フルートで吹きたい定番J-POPS』は、カラオケ伴奏のCDが付属。聞き慣れた曲が多く、練習しやすい構成です。
まとめ
フルートは小さなお子様からご年配の方まで、幅広く楽しめる楽器です。優雅な音色からジャズのような渋い吹き方まで、あらゆる演奏ができるフルート。横に構える独特なスタイルもフルートの魅力です。クラッシクやポップスなど、お好きなで楽しみながら吹いてみてくださいね。
藤加祐子 /
ビギナーズ編集部 ライター
仙台市出身在住。フリーライター・写真家・タティングレース作家。古書店巡りとフルート演奏が趣味。仙台フィルの演奏を聴くのが自分へのご褒美です。